平和特集
「教会史における平和主義の変遷と悲劇」
和解委員会 宮崎 誉
米ソ冷戦時代が幕を閉じ、21世紀を迎え、人々が共生の時代を夢描いた頃、2001年9月11日にニューヨークの貿易センタービルにハイジャックされた旅客機が突入する同時多発テロが起きました。その後、米国はアフガニスタンとイラクへの戦争に舵をきります。その頃、私は米国に留学し、平和学の盛んなメノナイト派の神学校で学ぶ機会を得ました。
あの頃、多くの日本人が教会に問いかけたことは、「なぜキリスト教を背景に持つ国が、戦争をするの?」という問いです。未信者だけでなく、日本人のクリスチャンも、主イエスは「あなたの敵を愛しなさい」(マタイ5:44)と教えたはずなのに、特に欧米のキリスト教を背景に持つ国々では、矛盾に感じないかと問いました。
キリスト教会の歴史を見ていくと、初期の教会は、絶対平和主義の立場だったことがわかります。そのことを表す初代教会の文献は多く残されていて、三世紀の教会教父のテルトゥリアヌスはこう語ります。主は「ペテロから武器を収めさせ(disarm)、すべての兵士にベルトをとらせた。キリスト者の男性が、如何にして戦争することができようか。いいえ、できないのである。また、平和な時に、主が取り去られた剣をもたなかったとしても、どのようにして〔軍人として〕仕えることができるだろうか」。また、既に軍隊に入っている者に対しては、契約期間中の離脱は死刑を意味するので、「戦争に行くのはよいが、殺してはならない」と語りました。別の教父のオリゲネスは「私たちは、もはや剣を他国に向けることをしない。また私たちはもはや戦争を学ばない。私たちはイエスさまのおかげで平和の子になったのだから」と語っています。殉教者ユスティノスは「私たちは、すでに一度、互いに〔キリストにあって〕殺されている。互いに戦争をするのみならず、尋問者に偽りもうそも言うことのないようにしよう。私たちはキリストを告白するために、喜んで死ぬのである」と語ります。歴史家によると、170年まではキリスト者が軍隊にいた記録は見つからず、173年の記録に現れます。ケルソスという人物は、キリスト者が兵役に着かないことを激しく非難する言葉を語っています(2003年『いのちのことば』誌、連載記事、藤原淳賀)。これらの初代教会の証言は、現代のキリスト者が読んでも、圧倒される証言です。
これほど明確に、福音の証しとして剣を放棄したキリスト教会が、どのように軍備容認へと変容してしまったのでしょうか。それは四世紀頃、特にローマ皇帝のコンスタンチヌス帝がキリスト教を容認し、後に国教化へ向かう課程において、起きていく変化です。教会の指導者アウグスティヌスは、個人的な倫理としては、自己防衛のためであっても他者を傷つける武器は持たないという信念をもっていました。しかし、教会と国家との関係が密接になってくるときに、無実な市民を悪しき敵の勢力から守る目的で、厳しい条件付きの戦争容認をしたのです。それが「正義の戦争論(just-war theory)」と呼ばれるものです。いくつかの条件項目を例に挙げてみます。
▽戦争に正当な理由がなくてはならない。▽合法的な権威(国家等)によって実施されなくてはならない。▽開戦前に正式に宣言されなくてはならない。▽戦争は紛争解決の最後の手段でなくてはならない。▽戦後に平和を実現する意図を持たなくてはならない。
それまでローマ帝国軍は周辺諸国を武力で蹂躙していました。その状況において、このような規制する条件を挙げて、皇帝や将軍が横暴に侵略戦争することを止めようと意図したのが、「正義の戦争論」のはじまりです。この思想は、現代でも国際法や国連の諸活動に適用されて、戦争抑制のために機能しています。しかしながら、歴史を見つめる時に、一度小さく容認した戦争への道が拡大解釈され、アウグスティヌスの意図を遥かに超えて、悲劇を生んでいきました。その結果、これまで迫害を受け殉教者であった教会が、迫害者に変容してしまったのです。
横暴な戦争を規制するルールを作り、戦争を抑制するという平和作りの取り組みは確かにあると思います。これは集団的自衛権の憲法解釈を閣議決定する動きをめぐって、政権内で公明党が平和主義の立場をどのように生かすか苦悩している姿に似ています。しかし、「大きく抑制するための小さな容認」は、後の時代に大穴となって船全体を沈める危険性を含んでいることは、私たちの教会の歴史が語りかけるメッセージだと言えないでしょうか。
このようなジレンマは、キリスト教を背景に持つ、米国においてまさしく言えることです。ラインホールド・ニーバーという米国の神学者がいます。彼は「キリスト教的リアリズム」として知られる思想を展開し、米国の多くの政治家が自身の愛読の神学者と名指しする思想家です。戦争を「必要悪」と理解し、容認し、正当化します。クリスチャンである大統領が米ソ冷戦時代のベトナム戦争や、核軍備拡張を行う上での思想的土台を提供した人物なのです。神学者J・H・ヨーダーは以下ことを指摘します。「ラインホールド・ニーバーが米国の軍備を正当化している立場は、厳密に物を考えようとしない米国の国粋主義者たちに悪用されて、ニーバー自身が受け容れられるよりもはるかに徹底的な軍国主義を正当化するのに役立たせられている」(『終末と平和』23頁)。
キリスト教では、どの倫理的立場であっても戦争は悪と見なすはずです。しかし、ニーバーの立場では世にはびこる「より大きな悪」から守るための「より小さな悪」として戦争を考えるのです。ところが「小さな必要悪」と見なされる戦争がナショナリズムやイデオロギーと結びつく時に、まるで催眠術にかかったように、自分たちは善をしていると思い込ませてしまうところに、罪の世の歪みがあると言えます。
歴史は繰り返すと言われますが、単調に反復するのではなく、螺旋的な渦のように深まっていくように思います。太平洋戦争の時代の国家と国家の戦いでは、国境線の攻防だったかもしれませんが、テロとの終わりなき戦いの時代に国境は盾にはなりません。また、米ソ冷戦時代に拡張された核兵器は、地球という星をまるごと壊せるほどの量を、人類は保持していると言われています。小さい穴から生じる渦が、私たち日本をどれほど深い闇に引きずり込んでいくのでしょうか。
ザベルカ神父(George Zabelka)というカトリックの司祭をご存知でしょうか。第二次世界大戦では、従軍司祭として米国の空軍に所属しました。彼は1945年8月9日に、核兵器(通称「ファットマン」)を搭載したB29爆撃機とそのパイロットを、聖職者として祝福の祈りをもって、長崎上空へ送り出しました。被爆国の日本人からは理解しがたいのですが、ザベルカ神父は原爆投下を正しいことだと信じ続けていたそうです。けれども、聖書から学び直す中で、彼は自分が「国家の敵は神の敵」と思い込んでいたことが、誤りであることに気づき、戦争に対する思想的回心を経験します。カトリックの司祭が祝福の祈りを捧げて送り出した核兵器が、日本におけるカトリックの中心地を破壊し、長崎の市街と共に、長崎の教会と修道院を破壊したことは歴史の悲劇であると言わざるをえません。回心後のザベルカ神父は、原爆被爆地への謝罪と、核廃絶運動や平和活動に身を投じていきます。
あの頃、多くの日本人が教会に問いかけたことは、「なぜキリスト教を背景に持つ国が、戦争をするの?」という問いです。未信者だけでなく、日本人のクリスチャンも、主イエスは「あなたの敵を愛しなさい」(マタイ5:44)と教えたはずなのに、特に欧米のキリスト教を背景に持つ国々では、矛盾に感じないかと問いました。
キリスト教会の歴史を見ていくと、初期の教会は、絶対平和主義の立場だったことがわかります。そのことを表す初代教会の文献は多く残されていて、三世紀の教会教父のテルトゥリアヌスはこう語ります。主は「ペテロから武器を収めさせ(disarm)、すべての兵士にベルトをとらせた。キリスト者の男性が、如何にして戦争することができようか。いいえ、できないのである。また、平和な時に、主が取り去られた剣をもたなかったとしても、どのようにして〔軍人として〕仕えることができるだろうか」。また、既に軍隊に入っている者に対しては、契約期間中の離脱は死刑を意味するので、「戦争に行くのはよいが、殺してはならない」と語りました。別の教父のオリゲネスは「私たちは、もはや剣を他国に向けることをしない。また私たちはもはや戦争を学ばない。私たちはイエスさまのおかげで平和の子になったのだから」と語っています。殉教者ユスティノスは「私たちは、すでに一度、互いに〔キリストにあって〕殺されている。互いに戦争をするのみならず、尋問者に偽りもうそも言うことのないようにしよう。私たちはキリストを告白するために、喜んで死ぬのである」と語ります。歴史家によると、170年まではキリスト者が軍隊にいた記録は見つからず、173年の記録に現れます。ケルソスという人物は、キリスト者が兵役に着かないことを激しく非難する言葉を語っています(2003年『いのちのことば』誌、連載記事、藤原淳賀)。これらの初代教会の証言は、現代のキリスト者が読んでも、圧倒される証言です。
これほど明確に、福音の証しとして剣を放棄したキリスト教会が、どのように軍備容認へと変容してしまったのでしょうか。それは四世紀頃、特にローマ皇帝のコンスタンチヌス帝がキリスト教を容認し、後に国教化へ向かう課程において、起きていく変化です。教会の指導者アウグスティヌスは、個人的な倫理としては、自己防衛のためであっても他者を傷つける武器は持たないという信念をもっていました。しかし、教会と国家との関係が密接になってくるときに、無実な市民を悪しき敵の勢力から守る目的で、厳しい条件付きの戦争容認をしたのです。それが「正義の戦争論(just-war theory)」と呼ばれるものです。いくつかの条件項目を例に挙げてみます。
▽戦争に正当な理由がなくてはならない。▽合法的な権威(国家等)によって実施されなくてはならない。▽開戦前に正式に宣言されなくてはならない。▽戦争は紛争解決の最後の手段でなくてはならない。▽戦後に平和を実現する意図を持たなくてはならない。
それまでローマ帝国軍は周辺諸国を武力で蹂躙していました。その状況において、このような規制する条件を挙げて、皇帝や将軍が横暴に侵略戦争することを止めようと意図したのが、「正義の戦争論」のはじまりです。この思想は、現代でも国際法や国連の諸活動に適用されて、戦争抑制のために機能しています。しかしながら、歴史を見つめる時に、一度小さく容認した戦争への道が拡大解釈され、アウグスティヌスの意図を遥かに超えて、悲劇を生んでいきました。その結果、これまで迫害を受け殉教者であった教会が、迫害者に変容してしまったのです。
横暴な戦争を規制するルールを作り、戦争を抑制するという平和作りの取り組みは確かにあると思います。これは集団的自衛権の憲法解釈を閣議決定する動きをめぐって、政権内で公明党が平和主義の立場をどのように生かすか苦悩している姿に似ています。しかし、「大きく抑制するための小さな容認」は、後の時代に大穴となって船全体を沈める危険性を含んでいることは、私たちの教会の歴史が語りかけるメッセージだと言えないでしょうか。
このようなジレンマは、キリスト教を背景に持つ、米国においてまさしく言えることです。ラインホールド・ニーバーという米国の神学者がいます。彼は「キリスト教的リアリズム」として知られる思想を展開し、米国の多くの政治家が自身の愛読の神学者と名指しする思想家です。戦争を「必要悪」と理解し、容認し、正当化します。クリスチャンである大統領が米ソ冷戦時代のベトナム戦争や、核軍備拡張を行う上での思想的土台を提供した人物なのです。神学者J・H・ヨーダーは以下ことを指摘します。「ラインホールド・ニーバーが米国の軍備を正当化している立場は、厳密に物を考えようとしない米国の国粋主義者たちに悪用されて、ニーバー自身が受け容れられるよりもはるかに徹底的な軍国主義を正当化するのに役立たせられている」(『終末と平和』23頁)。
キリスト教では、どの倫理的立場であっても戦争は悪と見なすはずです。しかし、ニーバーの立場では世にはびこる「より大きな悪」から守るための「より小さな悪」として戦争を考えるのです。ところが「小さな必要悪」と見なされる戦争がナショナリズムやイデオロギーと結びつく時に、まるで催眠術にかかったように、自分たちは善をしていると思い込ませてしまうところに、罪の世の歪みがあると言えます。
歴史は繰り返すと言われますが、単調に反復するのではなく、螺旋的な渦のように深まっていくように思います。太平洋戦争の時代の国家と国家の戦いでは、国境線の攻防だったかもしれませんが、テロとの終わりなき戦いの時代に国境は盾にはなりません。また、米ソ冷戦時代に拡張された核兵器は、地球という星をまるごと壊せるほどの量を、人類は保持していると言われています。小さい穴から生じる渦が、私たち日本をどれほど深い闇に引きずり込んでいくのでしょうか。
ザベルカ神父(George Zabelka)というカトリックの司祭をご存知でしょうか。第二次世界大戦では、従軍司祭として米国の空軍に所属しました。彼は1945年8月9日に、核兵器(通称「ファットマン」)を搭載したB29爆撃機とそのパイロットを、聖職者として祝福の祈りをもって、長崎上空へ送り出しました。被爆国の日本人からは理解しがたいのですが、ザベルカ神父は原爆投下を正しいことだと信じ続けていたそうです。けれども、聖書から学び直す中で、彼は自分が「国家の敵は神の敵」と思い込んでいたことが、誤りであることに気づき、戦争に対する思想的回心を経験します。カトリックの司祭が祝福の祈りを捧げて送り出した核兵器が、日本におけるカトリックの中心地を破壊し、長崎の市街と共に、長崎の教会と修道院を破壊したことは歴史の悲劇であると言わざるをえません。回心後のザベルカ神父は、原爆被爆地への謝罪と、核廃絶運動や平和活動に身を投じていきます。
(2014年8月「りばいばる」誌)
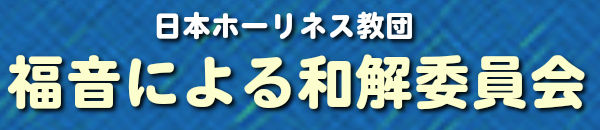


 「テロ等準備罪」抗議共同声明
「テロ等準備罪」抗議共同声明 教育勅語の閣議決定に対する抗議文
教育勅語の閣議決定に対する抗議文
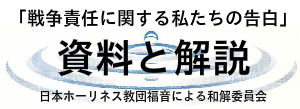



 戦争責任告白に基づく 戦後70年の祈り
戦争責任告白に基づく 戦後70年の祈り 戦争責任告白に基づく戦後70年の祈り(韓国語)
戦争責任告白に基づく戦後70年の祈り(韓国語) 戦争責任告白に基づく戦後70年の祈り(日韓対訳)
戦争責任告白に基づく戦後70年の祈り(日韓対訳)